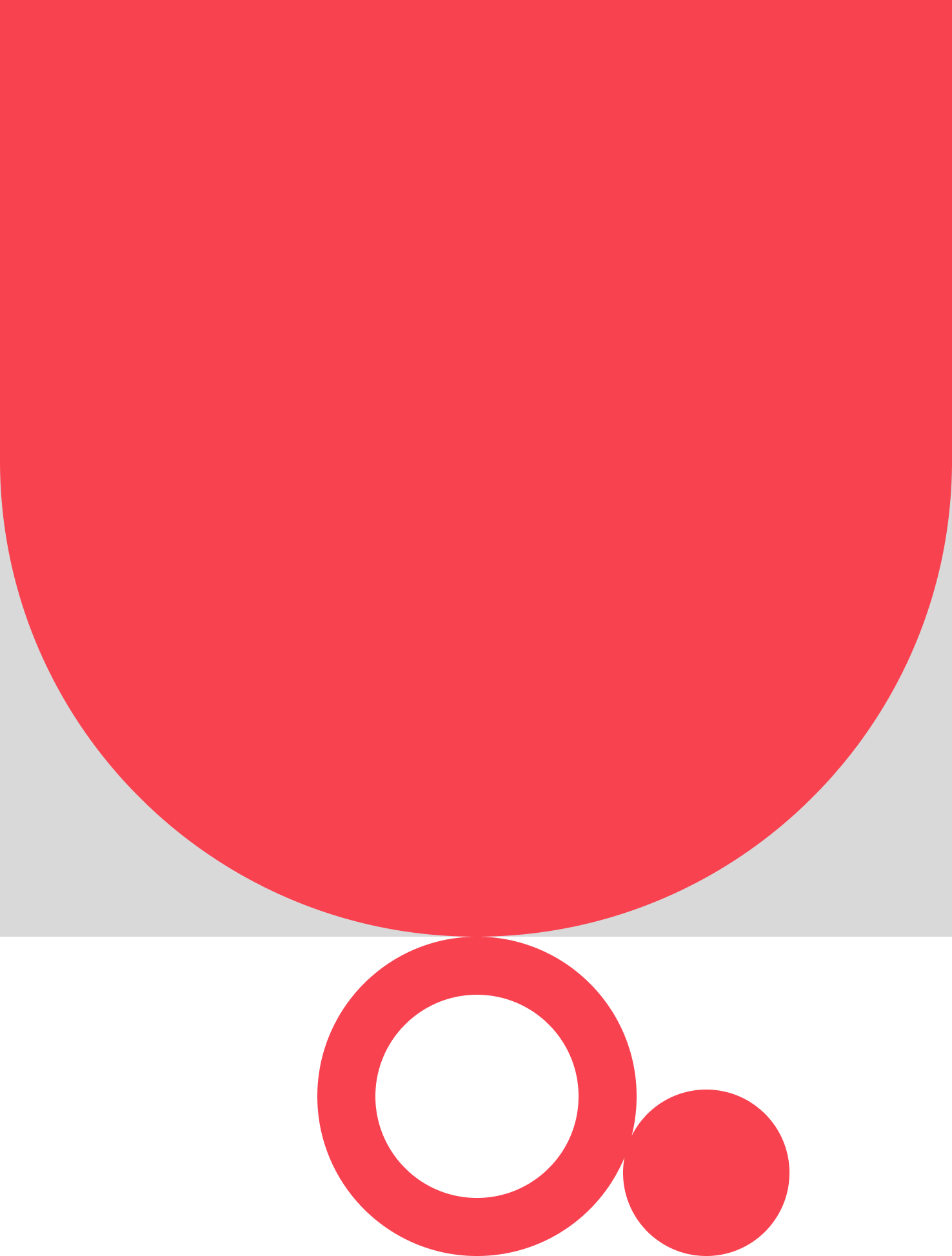【ミライデザイン研究所】 浮世絵という素材で見せる スピリット・オブ・ジャパン -後編-
2022.03.31
クリエーティブ局 デザイナーのOです。 【ミライデザイン研究所】とはーーー 空間デザインの領域から一歩外に飛び出し、 考え方やデザインの成り立ちについて考察、予想しアイデアにプラスしていく、そんな企画です。 前編に引き続き、現在角川武蔵野ミュージアムで開催中の「浮世絵劇場 from Paris.」についてお届けします。 江戸時代初期に庶民の間にも浸透した「浮世=現世」を表す絵画、浮世絵は 今で例えるとSNSなどの、誰もが楽しめる身近なメディアだったようです。 時代を超え、ヨーロッパに渡ったあとも、ゴッホやモネなどの著名な画家たちに大きな影響を与えたと言われています。 今回の展示では浮世絵劇場というタイトルの通り、展示室は大きな劇場と化しており、 360°を浮世絵を再構築した映像が映し出されていました。 この企画を体験して感じた下記2点、 ①浮世絵を再構成して見せることの意味 ②没入感の高い体験を生んでいる空間の工夫の考察 のうち、後編では②についてお送りします。 ②没入感の高い体験を生んでいる空間の工夫の考察 先述したような没入感の高さを生んでいる要因はもちろん映像だけでなく、空間の役割も大きいように感じました。 この企画の会場構成は以下のようになっています。 360度シアターは第一部、それを鑑賞した後に第二部ではダニーローズ・スタジオがインスピレーションを受けた作品の紹介や、 現代作家たちが描く新たな浮世絵などの展示となります。 ◆前室 この企画の概要を解説したり、注意事項の説明を受けるための部屋です。 それと共に第一部での360度シアターへの期待感を高めるための仕組みでもあります。 ほかの一般的な展覧会などでは、入場するとすぐ展示品が目に入ってくるようなところ多くあるかと思います。 しかしこの企画ではあえて前室と第一部のシアターエリアまでに長い廊下を設置する事で、 このあと目に飛び込んでくるインスタレーションのインパクトをより大きなものにしているのです。 ◆第一部_360度シアター メインの展示であるインスタレーションのエリアとなります。 長い廊下を抜けた先に、巨大な空間が目に飛び込んでくる際のインパクトはかなり大きいものでした。 鑑賞者はこの広い空間を自由に移動しながら楽しむことが可能です。 映像が投影される壁面に近づいても良し、中央の柱の間に設置されたベンチで広い範囲をゆったりと眺めながら鑑賞することも良し。 決まった体験の仕方は存在しないのです。 そうした自由な鑑賞方法をとりつつも、ほかの鑑賞者の邪魔をしないテクノロジーや空間の工夫に幾つか気付きました。 一つはベンチや柱の仕様です。 柱の側面位置や人の座るベンチなど、どうしてもプロジェクションマッピングによる映像を投影することが難しい箇所が存在します。 今回の展示ではそのような箇所にミラー素材を貼ることによって、 実際には映像が投影されていない場所にも空間の奥行きが感じられるように、設計されていたのだと思います。 もう一つがプロジェクターの設置台数、そして位置です。 自由に位置を移動して鑑賞するという事は、移動する位置によっては投影する映像を遮り、影になってしまう可能性があるという事です。 それを解消するために、今回の展示では緻密な計算の基にプロジェクターの位置が決定されたのではないかと思います。 実際に壁の近くに立ってみると、確かに床の映像は影になっていますが、 壁の映像は人が立っていても影になってしまうことはありません。 もちろん場所によってはそうではない箇所もありますが、かなり細かく投影する角度を検証しながら決定していったからこそ、 座って鑑賞する人たちのことも邪魔することなく、移動しながら鑑賞できる、没入感を実現できたのではないでしょうか。 ◆第二部 最後に、この展示に関連する浮世絵などの情報が知れる展示エリアとなります。 以前ご紹介した「北斎づくし」の映像作品では、 「事前に実物を鑑賞したからこそ、映像を見た時の理解度が上がる」という事をお話しましたが、 こちらのやっていることは真逆です。 北斎づくしの映像作品は「理解を深めたうえで、更に鑑賞者を引き込ませるためのツール」という立ち位置だったのに対し、 今回の展示の趣旨は「まずは小難しいことは考えずに、 ファーストインパクトで浮世絵のすばらしさを知ってほしい」だったのだと思います。 元々浮世絵というものに興味のない人でも、親しんでもらおうとする姿勢が、このような展示のゾーニングに繋がっています。 実際に会場に足を運んだ際も、映像を見終わった後に詳しい情報を入れることで、一歩先の理解につながるような感覚がありました。 目的やターゲット、企画の趣旨によってゾーニングを変えていく事で、 体験の質そのものが変化していくことの良い例なのではないでしょうか。 ◆まとめ 今回は映像を使ったインスタレーション作品の企画展について、分析や所感を述べさせていただきました。 ただ作品を展示をするだけではなく、より没入感の高い経験を鑑賞者にしてもらうことによって、 記憶に残すような手法を用いることが増えていますが、 それもただ映像を使うだけだったり、体験を入れ込むだけでは質の高い体験や没入感は生まれません。 鑑賞者の動きや展示の趣旨、伝えたいことを軸に置いたうえで、それに沿った空間設計、コンテンツ作成をする必要性があると思います。 それこそが「Experience Design」であるのではないでしょうか。 ご紹介した展示は、5月8日まで会期を延長して、角川武蔵野ミュージアムで開催されております。 今回の記事ではご紹介できなかった映像作品の他の幕や、第二部の展示内容もありますので、ぜひ実際に体験してみてください。 ■参考 ・公式サイト:https://kadcul.com/event/50 ・美術手帳 オンラインマガジン:https://bijutsutecho.com/magazine/news/report/24767