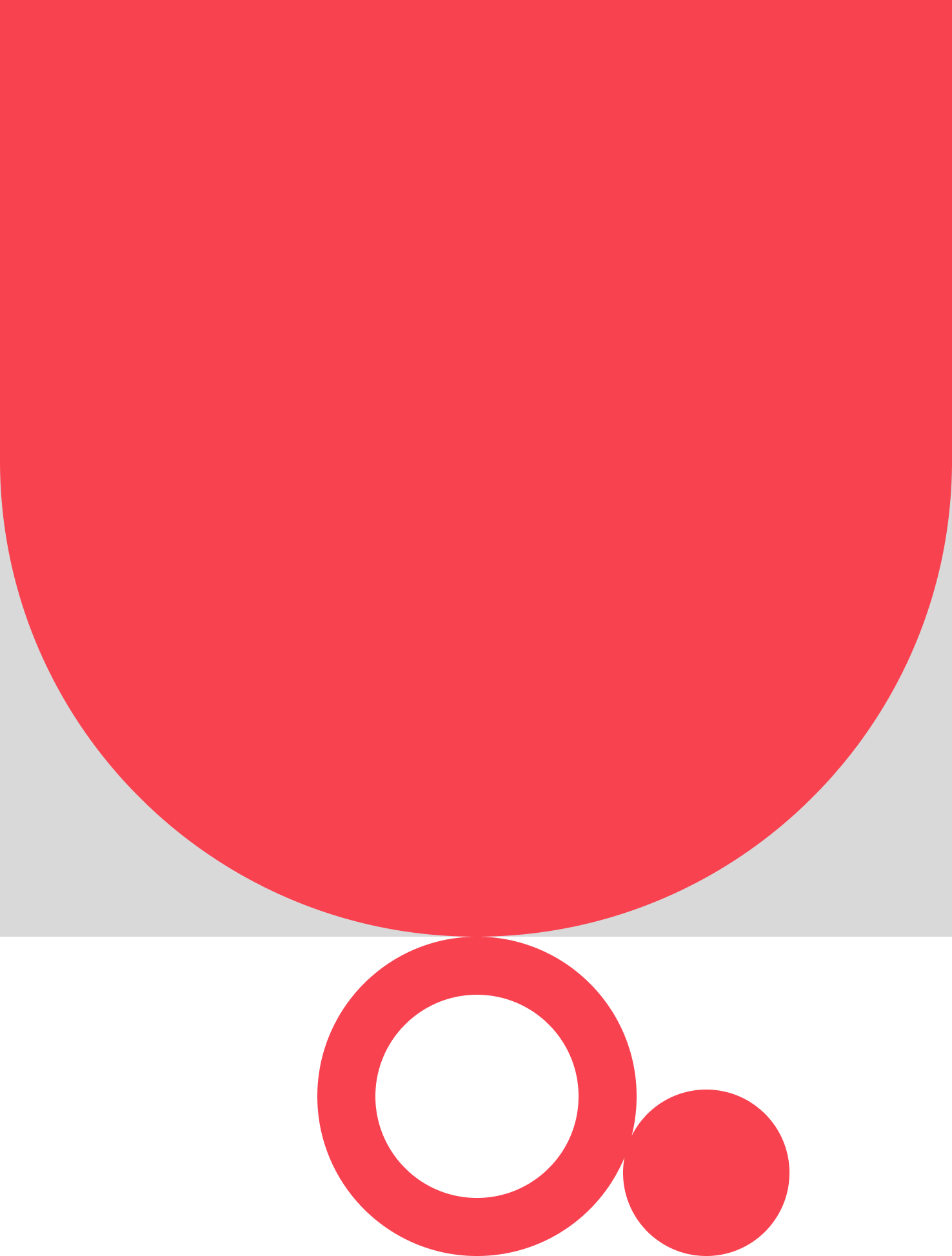【ミライデザイン研究所】鑑賞する絵画から、体感する絵画へ -後編-
2022.08.22
クリエーティブ本部 デザイナーのIです。 【ミライデザイン研究所】とはーーー 空間デザインの領域から一歩外に飛び出し、 考え方やデザインの成り立ちについて考察、予想しアイデアにプラスしていく、そんな企画です。 前編に引き続き、現在日本橋三井ホールで開催中の日本初の没入体験型ミュージアム 「Immersive Museum(イマーシブミュージアム)」についてお送りします。 このイベントを体験して感じた下記の2点、 ①作品世界により深く入り込ませるための要素 ②没入体験を最大化するための工夫 のうち、後編では②について考察します。 ②没入体験を最大化するための工夫 ◆入口 絵画の世界が広がった空間へ誘導する前に、プロローグとして絵画についてや、 印象派が生まれた背景などを読みながら入る形になっていました。 映像のみの展示になるので、最初に言葉で時代の背景を頭に入れ、そこから体験することで、 絵画の世界にスムーズに入り込んでいけると感じました。 ◆黒いカーテン HPやこちらのフォトスポットにもなっていますが、黒いカーテンが会場入口にもあり、そこから展示に入れるようになっていました。 入口付近も全体的に暗くなっていて、真っ暗なカーテンの隙間からカラフルな映像が見えるような演出がされていました。 来場者のワクワク感を高めると同時に、カーテンをめくって中に入るという動作が伴うので、 "入り込んだ"という没入感が高まっているのではないかと思いました。 ◆Café & Giftエリア Immersive Museumでは、Café & Giftエリアも展開しており、印象派をモチーフにしたドリンクやフードも提供されており、 ここでも絵画の世界に浸れるような工夫がされていると思いました。 こちらのクリームソーダはクロード・モネ『日の出』『睡蓮』『睡蓮の池と日本の橋』がイメージされていて、 飲みながら色の混ざり合いを楽しむことができました。 また、このエリアでは、サウンドアーティストYuu Udagawaによる サウンドインスタレーション作品『水紋~Water Crest~』が空間展示されており、 サウンドスケープ(音風景)という概念を元に、「音楽」で、水紋のように、流動的な変化を感じさせるような工夫がされていました。 空間全体で絵画の世界を五感で感じられるようになっていると感じました。 グッズ販売でも色とりどりなものが多く、Immersive Museumで感じた絵画の世界を実体験として鑑賞し、 カラフルな思い出を持ち帰れるような形になっていました。 まとめ これまでは美術館の壁にかけられていた額縁の世界を見るという芸術体験でしたが、 ここでは画家たちの作品の世界の中に自分たちが“入り込む”ことができました。 鑑賞する絵画から、体感する絵画へと変わったことで、今回の企画では、19世紀の時代に作家が感じていた時間の流れや光の動きを、 現代的な解釈を加えた新しい視点で体験することができ、多くの発見がありました。 世界中で“没入感”への需要が急激に高まっていて、 没入感が求められるのはゲームやアートだけでなく、イベントシーンでも注目されています。 そこで考えておきたいこととしては、何を見せる・展示するのか、ではなく、来場者側にどう感じてもらうかというところだと思います。 そこを踏まえた上で、技術を用いて空間を意識した奥行き感や立体感のある映像で臨場感を表現したり、 視覚だけではなくさらに音を加えるなどの、『五感』で没入感を高める仕組みが必要だと感じました。 ご紹介した展示は、10月29日まで、日本橋三井ホールで開催されております。 ぜひ実際に新しい絵画の体験をしに、足を運んでみてください。 【参考】 「Immersive Museum」公式サイト:https://immersive-museum.jp/ Immersive Museum.“日本初!音と映像により視覚体験を超えた絵画の世界に没入する体験でモネら印象派を味わい尽くす"飛び込むアート"を 日本橋三井ホールにて「Immersive Museum」開催決定”. PR TIMES. 2022-4-20. https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000054201.html, (参照2022-08-04)